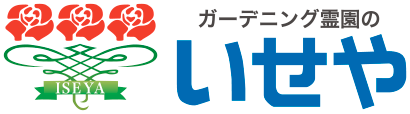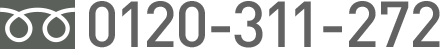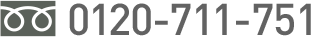「季刊誌ふれあい」デジタル版
「終活って、まだ先の話?」と思うあなたへ。今こそ始めたい、家族と自分の“これから”を整える準備
目次
終活――それは、「これから」を心地よく生きるための準備。
人生の節目に立ち止まり、自分らしく、そして家族に優しく未来を整えていくこと。
最近では「大切な人に迷惑をかけたくない」「想いをちゃんと伝えたい」と、終活を前向きに捉える方が増えてきました。
今回は、家族との関係、財産、そして遺言についてなど、終活で考えておきたい大切なことをテーマに、終活サポートの専門家である『トリニティ・テクノロジー株式会社』の三瓶さんに、わかりやすくお話を伺いました。

トリニティ・テクノロジー株式会社
三瓶さん(左) 濱中さん(右)
1. 終活の手始めに ──「3本の柱」で人生を整理するヒント
- 最近「終活」という言葉をよく聞きますが、実際には何から始めたらいいのか、いまひとつイメージが湧かなくて…。生前にやっておくと良いことって、具体的にはどんなことがあるんでしょうか?
三瓶さん(トリニティ・テクノロジー株式会社)
私たちは、終活における準備としていつも「3本の柱」についてのお話をしています。それは…
○ 家族関係の棚卸
家系図や相続関係、家族の過去のトラブルや気になる関係性を整理します。
○ 財産の棚卸
預貯金、不動産、保険、有価証券、負債など、財産の全体像を整理します。
○ 供養・お墓・葬儀の棚卸
どのような形で供養したいか、希望するお墓や葬儀のスタイルなどを考えます。
この3本の柱をしっかり準備しておくことで、「自分がいなくなった後、家族に迷惑をかけない」ための道筋をつけることができるんです。
2. “うちは普通の家”こそ作ってみてほしい。心がつながる家系図の魅力

「3本の柱」で考えると、終活ってすごく整理しやすくなるんですね。何から始めていいか分からない人にとっても、いい道しるべになりそうです。

「全部やらなきゃ」と思うと身構えてしまいますが、この3つに分けるだけで、ぐっと取り組みやすくなります。まずは気になるところから、少しずつ手をつけていけば大丈夫ですよ。
- 1つ目の家族関係の棚卸にある『家系図』って、相続のタイミングではあまり話を聞かない気がしますが必要なものなんでしょうか?
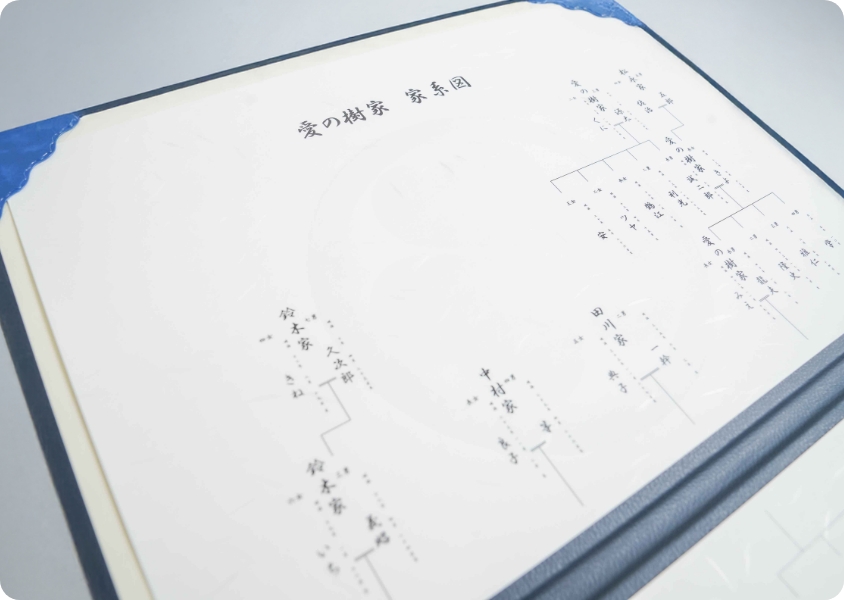
『家系図サービス あいのき』家系図 イメージ
三瓶さん(トリニティ・テクノロジー株式会社)
確かに相続の際には相続関係が明らかになっていれば良いと考えられる方が多いと思います。
実際その通りなんですが、家系図というのは家族の歴史を紐解いていく作業です。
基本的に弊社で家系図づくりのご相談をいただいた際は「直系尊属」といって、ご依頼人から見たご先祖様をすべて調査します。
一般的にはご依頼人からみた、父、祖父、曾祖父、さらには高祖父あたりまで遡ることができます。もちろん、祖母側の情報も同様に取れます。これは正直なところ、実際に調査してみないと分からない部分も多いんですね。
- なるほど。普通のご家庭でご先祖様の歴史を遡っても、特に語るようなストーリーは見当たらない気がしてしまうのですが、どうなんでしょう?
三瓶さん
今おっしゃられたように「うちは普通の家だから、特に語るような物語はない」と思われる方も多いですが、実際はそんなことはありません。自分の両親、その両親…と、家系を遡っていくと、必ず何かしらの歴史があります。
これまで、戦争や震災、疫病の流行など、さまざまな時代を生き抜いてきた人々がいて、今の自分に繋がっているわけです。家系図を作る過程で、郷土資料などを調査することもあり、思いがけないご先祖のエピソードが見つかることもあります。
三瓶さん
実は個人的なお話になりますが、私の曾祖母はごく最近まで存命でした。100歳まで生きて、つい3週間前に亡くなったんです。普段ご相談いただくお客様に家系図の大切さをご説明して、数多く調査もしてきましたが、それまで自分のルーツに関してはしっかり調べたことはなかったんですよね。
そういったこともあって、これを機に自分自身のツールも探ってみようかと。
そうしたら今まで知らなかった面白いエピソードがいくつも出てきました。
その中の1エピソードとして、私の曾祖父の話があります。
曾祖父は第2次世界大戦に出征していて、当時は得撫島(うるっぷとう)という場所にいたそうです。陸軍で、どうやら大砲を扱っていたようで、その後、武装解除されたのち、 3年間シベリアに抑留されていました。
過酷な環境だったと思いますが、無事に帰国して、そこから家族が繋がっていると思うと感慨深いですよね。
また別のエピソードでは、福島県に私の親族の方がいて、昔、飢饉のときに自分の田畑で育てた作物を地域に分け与えたことで表彰されたという記録が出てきたんです。
私も全く知らなかった話で、郷土資料を読み解く中でわかって。
家系図を調べなければわからなかったことだらけでした。
- とても面白いお話ですね!知らなかった親族がいることに気づいたり、家族の意外な一面を知れたりするのも、ちょっとワクワクします。

三瓶さん
はい。それと、家系図を作るにあたってはもう一つ大事なことがあります。戸籍や戦争記録だけでは「公的な情報」にすぎません。そこには“心”や“声”がありません。 だからこそ、今生きているご家族にヒアリングすることがとても大切なんです。
でも実際、自分でやろうとすると恥ずかしくて、なかなか聞けなかったりしますよね。
- 分かります。親に聞くのもちょっと照れくさいですし、祖父母に聞くのも、話したがらないこともありますし。
三瓶さん
だからこそ、私たちのような「第三者」がヒアリングをする意義があります。関係ない第三者だからこそ、皆さん率直に話してくださる。
その中には、ご先祖様の話だけでなく、ご自身の親に対する感謝の気持ちまで出てくることもあります。それらもすべて記録化して、文章にして、家系図の一部としてお渡ししています。
家系図を作ることの価値って、単に記録するだけでなく、今のうちにご家族に話を聞いておくこと、想いを受け継ぐこと――これが本当に大切なんです。
受け継がれてきた歴史も含めて大切にする。記録としてだけでなく、物語として家族を知る。
私はそれを「心の承継」と呼んでいます。
最近では両親や祖父母に向けて、家系図をプレゼントする方も増えてきてるんですよ。
- 家系図をプレゼントにする、という発想はなかったのですが、今お話を伺っていると、すごく素敵な贈り物になりますね。
三瓶さん
私自身、家系図を作って、自分の親、祖父・祖母、さらには叔父や叔母にまでプレゼントしたことがあるんですが、ものすごく喜ばれました。
家系図作りはその家にとって一大プロジェクトです。
一生に何度も作るものではなく、基本的には一度作って、代々受け継いでいく“家の記録”になります。
かなり難しい堅苦しいイメージに思われるでしょうが、自分でも簡単な家系図は作れますよ。
たとえば、自分→両親→祖父母くらいの関係性を図に起こすことなら可能です。
簡単な家系図を作っておくだけでも、いざ相続が必要な状況になったときにスムーズに段取りを進めやすくなります。最近ではコンビニでも、マイナンバーカードがあれば戸籍が取れます。

『家系図サービス あいのき』家系図、家系書類、ピープルストーリー イメージ
3. 相続トラブルを防ぐ第一歩。「財産の棚卸」で知っておくべきこと
- “家族の棚卸”を終えた後に、”財産の棚卸”が必要になりますね? イメージでいうと預貯金とか、家の有無とか、あと保険に入ってる、入ってないとかっていうところかと思うのですが。
三瓶さん(トリニティ・テクノロジー株式会社)
財産と一口にいっても、「積極財産」と「消極財産」という2つの財産に分けられるんです。
積極財産というのは、預貯金、不動産、有価証券、保険、あと骨董品や貴金属、ゴールドなど。これはプラスの財産を指します。
消極財産というのは、端的に言うと借金のことで、例えばカードローンがある、クレジットカードの残債がある、住宅ローンが残ってるといったものですね。これも全部「財産」なんですよ。
大事なのは、プラスだけじゃなくて、マイナスの財産もちゃんと把握しておくこと。
特に一番大きいのは住宅ローンです。
多くの家では団信(団体信用生命保険)に入っているから、亡くなったら全部完済されます。ただ、たまに入ってない方もいらっしゃいます。
そうすると、たとえば預貯金が1,000万円あっても、住宅ローンも同じくらいの金額があれば、結局ほぼ残らないということもあるんです。
- 自分の両親がどれくらい借金をしていて、住宅ローンが何年残っていたのかなんて、子供って知らないことがほとんどですよね。
でもそれを面と向かって聞くのは、いくら両親であってもなかなか話題にしにくいですね…。
三瓶さん
先ほどの家系図の話じゃないですが、こういった”財産の棚卸”の段階でも「第三者の目」を入れることって、けっこう大事です。
“財産の棚卸”だけでも、第三者の専門家に相談して状況を把握したうえで、相続が必要なタイミングになったらご自身で対応しても構わないんです。
とにかく「状況を把握する」ということが重要です。
- この”財産の棚卸”に関して、例えば第三者の専門家にご依頼する際に、やっておいたほうが良いことはありますか?
三瓶さん
使っていない銀行口座とかクレジットカード、こういうのは解約しておいてほしいですね。
残高がゼロだったとしても、基本的には相続が発生した後に解約することになります。そうすると当然、手間もかかりますし、お金もかかってしまう。
あとは不動産の権利関係です。不動産が共有名義になっている場合。たとえば親が、すでに亡くなっている配偶者の方や、何世代か前のご先祖様と共有しているケースもあったりします。
もし共有名義になっているのなら、それを事前に解消するようにしておいた方がいいですね。
4.エンディングノートと遺言書の正しい使い分け

終活って難しいイメージがすごく強かったのですが、
これまでのお話の中で終活に関して前向きに考えられそうな気がしてきました!

よく難しいと思っていらっしゃる方が多いですが、
順を追って整理していけば難しい話ではないんですよ。
- “財産の棚卸”を終えたら、それをどう家族に残していくかを考える必要がありますね。 エンディングノートを書いておいたほうがいい、という声も多く聞きますが、実際どうなんでしょう?
三瓶さん(トリニティ・テクノロジー株式会社)
エンディングノート、とても良いと思います。
今日お話ししているような「財産」「家族関係」「お墓・供養」などの“棚卸”をするうえで、最初のステップとしてとても役立ちます。
ただ、注意したいのは「エンディングノートには法的効力がない」という点です。
- つまり、そこに「この財産は誰にあげたい」と書いてあっても、実際には効力がないということですね。
三瓶さん
はい、まさにその通りです。
「うちの両親は“全部私にあげる”って言っていた」とおっしゃる方や、「エンディングノートにこう書いてあるから」と持って来られる方もいらっしゃいますが、それだけでは財産分与はできません。
民法に基づいた正式な形式で「遺言書」を作成しないと、法的には無効になります。
エンディングノートは「想いを整理するツール」としてはとても良いのですが、財産の承継にはやはり遺言書が必要です。
- 遺言書にも種類がありますよね。自筆証書とか公正証書とか。どちらがいいんでしょう?
三瓶さん
自筆証書遺言の場合、全文を自分の手で書き、日付・署名・押印があれば有効です。
あとは、どの財産を誰にどれだけ残すかを明確に記載することが大切です。
注意点もいくつかあります。
日付がなかったり、押印が漏れていたりすると、その遺言は無効になってしまいます。
また、内容に矛盾がある場合も要注意です。たとえば、第一条で「不動産は長男に」と書いておきながら、第三条でそれに反する内容があった場合などですね。
対して公正証書遺言は、公証役場で公証人立ち会いのもと作成します。
専門家のチェックが入るので、法的にも非常に強い効力を持ちます。裁判になったとしても、証拠として非常に有効です。
もちろん費用はかかりますが、「絶対に失敗したくない」「トラブルを防ぎたい」という方には、公正証書遺言をおすすめしています。
- やはり専門家のチェックが入ったほうが安心ですね。
三瓶さん
あと、ドラマで直筆証書を誰かが盗んだりなんてシーンがありますが、「そんなの現実ではないよね」と思っていても、実際にあるんですよ。
実は遺言書が改ざんされた形跡があった、というケースもあります。
でも公正証書遺言なら、公証役場で保管されるので、万が一のリスク回避にもつながりますね。

5. “うちは大丈夫”が一番危ない!相続トラブルを防ぐためにできること

エンディングノートは想いを伝える手段、遺言書は法的に財産を残す手段なんですね。でも実際には、遺言書まで準備している人ってまだ少ないんじゃないでしょうか?

おっしゃる通りです。
準備を後回しにしてしまう方が多いのですが、相続の場面では、思わぬトラブルが起こることも珍しくないんですよ。
- 遺言書って、どうしても「特別な事情がある家庭の話」っていうイメージがあります。 どんな家庭でも揉める可能性ってあるんでしょうか?
三瓶さん(トリニティ・テクノロジー株式会社)
これは本当によくある誤解なんですけど、「うちは仲がいいから大丈夫」とか「うちの子どもたちは揉めない」っておっしゃる方ほど、実は危ないんですよね。
なぜなら、相続って単純な“お金の問題”だけで片付くことは少なくて、感情の問題が絡んでくるケースがとても多いんです。
たとえば、幼い頃に「兄弟姉妹の中で自分だけ親にあまり構ってもらえなかった」という思い出や、親の晩年の介護にどう関わったか――そういった背景が大きく影響するんです。
- たしかに…。親の介護をずっとしてきた兄弟と、ほとんど関わってこなかった兄弟が同じ割合で相続するってなると、ちょっと納得いかないかもしれませんね。
三瓶さん
はい。「法定相続分で分ける」場合であっても、遺言書があったほうがリスクに備えられます。
たとえば、預貯金の解約や不動産の名義変更などには、相続人全員の同意が必要になります。
「法律通りに分けるつもりだったけど、誰かが反対していて手続きが進まない」というケース、本当に多いんですよ。
- 家や土地なんて物理的に分けられませんもんね…。売るしかない。
三瓶さん
まさにそこが問題なんです。
土地や不動産は分けるのが難しいからこそ、「誰が相続するか」をしっかり遺言に明記しておかないと揉めてしまう。兄弟姉妹が複数いると、感情のすれ違いだけでなく、その配偶者が口を出してくることもあって、さらにややこしくなってしまうんです。
それにその土地が自分やご家族にとってとても価値のあるものだったら、売ってしまうのもどうなのかといった問題もあります。
だからこそ遺言書はしっかりと用意をしておく必要があります。
家族内に無用なトラブルを残さないためにも。
6.まとめ:人生の最後にできること──家族を守る“優しさの形”としての終活
三瓶さん(トリニティ・テクノロジー株式会社)
『家系図』は“心の承継”。『遺言』は“財産の承継”。
私たちのあいだでは、そう呼んでいます。
財産のことだけを考えると、相続って少し無機質に感じてしまいがちですが、そこに歴史や想いが重なることで、ただ人生の終わりに向けた準備じゃなく、前向きにとらえられるようになるんです。
そもそも終活は、「自分のため」だけにするものではないと個人的には思っています。
もちろん、自分の身辺を整えて旅立つためという意味もありますが、それだけでなく、残された子孫や家族がこれからも健やかに生きていくために準備しておくべきことでもあります。
たとえば、自分が残した財産がどこにあるか分からなかったり、借金があることを誰も知らなかったり…。
プラスの財産がたくさんあったとしても、遺言書がなかったばかりに、家族の間で争いが起きてしまうこともあります。
さらに、葬儀やお墓、供養のことなど、そういった心身ともに大きな負担を、残していく家族に背負わせたくはないですよね。
だからこそ、今のうちから「家族の棚卸」や「財産の棚卸」をしておいて、ある程度の道筋をつけておくこと。
それが、最後その人に残された一番大事な仕事なんじゃないかなって私は思います。

トリニティ・テクノロジー株式会社profile

「超高齢社会の課題を解決し、ずっと安心の世界をつくる」をミッションに掲げ、相続・終活・家族信託などに関するさまざまな課題に向き合う、リーガルテック企業。
2020年の設立以来、全国14拠点を展開し、年間20,000件以上の相続・終活に関するお問い合わせに対応。高齢化が進む日本において、家族の安心と資産の未来を守るためのサービスを幅広く提供している。
公式サイト